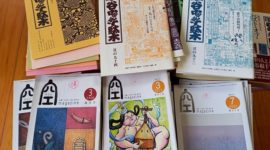木がうっそうと茂る西日暮里駅近くの諏方神社。高台で線路を見下ろせるので、近隣の親子には、電車がよく見える神社としても有名らしい(過去記事参照)。境内で10月6日、「みんなで木と遊ぶ」というアートワークショップが開かれた。「まちじゅうが展覧会場」を合言葉に10月から始まっている芸工展2024参加企画の一つだ。

ファシリテーターは美術家の青島左門さん(過去記事参照)。狛犬がいる神輿の保管庫の前に立ち、話し始めた。「最近の研究によれば、木の根っこの根圏菌(こんけんきん)が地中でつながっていて、日が当たらないところにある苗木に栄養を送って助け合っている。また、香り物質を通して木と木は会話しているそうです」

「今日は、木と木、そして木と人のつながりを、目に見えるように表現してみたいと思います」

境内には、別の場所から収集してきた木の枝やオレンジ色のカラスウリ、イガグリなどが並べてある。桜の木の前に立った青島さんは、「彫刻作品は重力から逃れることはできないんですが」と言いながら1本の枝を手に取って桜の幹に立てかけた。「バランスがとれていれば、小さな力でも立てることができます」。そして緑の草のようなものを手にし「このメヒシバを使って結んでいきます」

説明はこれだけ。「さあ、それでは生きている植物を感じながらつないでいってみてください」

参加者の親子はさっそく木の枝やカラスウリを手に取り、メヒシバを使って枝に結び付け、作品づくりにとりかかった。「どこにする?」「ここ、結んだ方がいいかな」。自由な発想で枝を立てたり、カラスウリを結び付けたり。

青島さんは「植物の世界は、会話したり助け合ったり、人間社会にも似ていると思う。目に見えなくても、地下でつながって、ひろがっている」と話す。自然素材を使ったワークショップは始めただそうだが、「みんなで作ることに意義がある。協力し合いながらなので作りやすいし、楽しい」

メヒシバを懸命に結んでいる子どもがいた。「あ、切れた」。何重にも結ぼうとしているので、すぐ切れる。つながった木の枝の下の部分がトンネルのようになり、小さい子はくぐって遊んでいた。

そのうち、木の枝もなくなってしまった。「境内で拾ったものを足していってもいいですよ」と青島さん。あちこちで、大人同士、子ども同士、会話している様子もみられる。雑談をすることもワークショップにおいて大事なことなのだという。「人によって参加度も違う。そこも大事に。やりたいときだけやればいいと思う」

実際、飽きてきた子はハトを追いかけまわしたり、木の枝で覆われておうちのようになった空間でかくれんぼしたり。思い思いのやり方で、作品はなんとなくできあがってきた。

サルノコシカケや木の実、草の実が飾られたり、枝豆(?)がぶら下げられたり、創意工夫がみられる。

せっかくなので、境内に落ちていた木の葉を何枚か拾って、木の枝の上に置いてみた。黄色い葉に緑色のまだら模様が入っているのがアートっぽくて、きれいだと思ったからだ。しばらくして、子どもがやってきてメヒシバをその葉っぱたちにブスブス刺し始めた。すると、また別の造形になった。なるほど、こうやって共同でやることによって、それぞれの思いが反映され、作品が変化していくのか。

作業に夢中になるほど、終わりがない。だから、1時間ほどで時間を区切って終了した。「さあでは、これで終わりにしましょう」

写真ではなかなか表しにくく、アート作品に見えないかもしれないが、実に立派な作品に仕上がった。

青島さんは「いい作品ができてびっくり」と言う。抽象的だが、生き物にみえる。「地中で根圏菌がこういう広がり方をしていると連想できるような形になった」と評価していた。

芸工展2024は、31日まで。谷根千のギャラリーやお店、原っぱ、記念館など、まさにまちじゅうで、60以上の企画がある。詳細はサイトで。(敬)